休職は人生を豊かにする可能性を秘めている
2022/4/12 最終更新
休職や離職は現代の日本社会において珍しいものではなくなりました。メンタルヘルス不調による休職者は年々増加しています。出来事として見れば珍しくなくても、当事者にとっては大きな喪失体験であり、重大なライフイベントです。
このライフイベントにどのような意味を持たせるかによって、その後の人生は変わってきます。近年注目されているPTG(心的外傷後成長)の概念をもとに説明したいと思います。
2022/4/12 最終更新
休職や離職は現代の日本社会において珍しいものではなくなりました。メンタルヘルス不調による休職者は年々増加しています。出来事として見れば珍しくなくても、当事者にとっては大きな喪失体験であり、重大なライフイベントです。
このライフイベントにどのような意味を持たせるかによって、その後の人生は変わってきます。近年注目されているPTG(心的外傷後成長)の概念をもとに説明したいと思います。

メンタルヘルスの不調により、仕事から離れなければならないという体験は、当事者にとってどのような意味を持つのでしょう。
職場がストレスの原因になっており、それがもとでメンタル不調を来たした場合、たとえば適応障害と診断されることがあります。その場合は、ストレスの原因から離れることが治療の第一選択であることはこれまでも説明してきました。
ところが、ストレスの原因である職場であったとしても、当事者にとっては生活の一部であり、それを失うことは心理的に大きな痛みを伴う経験になります。休職するということは、ストレス対処の一手段でありながら、同時に、当事者にとっては耐えがたい、つらい体験として感じられるのです。
このような、当事者にとって感じられる世界のあり方を、心理学の言葉で『内的現実』と言います。客観的な数値で測られる世界を外的現実とすれば、あくまで当事者の主観によって評価されるものが『内的現実』です。
そして、メンタルヘルス不調においては、ときにこの『内的現実』での評価のほうが外的現実より重要な意味を持つことがあります。他人から見てみるとささいな出来事でも、当事者にとっては大事件であった、という例を挙げてみればわかりやすいでしょう。
この『内的現実』を考えるとき、仕事という人生の一部をもぎ取られるような感覚は、一般的に想像されるよりずっと苦しいものであるかもしれません。「一時的に仕事から離れるだけじゃないか」と言う人もいる反面、自分の体の一部を奪われたように感じる人もいるのではないでしょうか。
このような体験はこころに大きな傷を残し、精神面に影響を与えます。この意味で、休職は一種のトラウマ(心的外傷)体験だと考えることができるのです。
ですので、もし、仕事を離れたことにより、一層精神的に不安定になったり、身体面で不調感が出たとしても、自然な反応と考えてください。自分は弱いと責める必要はどこにもないのです。
では、このようなつらく苦しい体験は、私たちにとってマイナスにしかならないのでしょうか。確かに、ストレスフルな状況や困難が長期化した場合、最悪の場合はPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する恐れがあります。PTSDについてはここでは述べませんが、深刻な症状を引き起こすメンタル不調です。大災害や、事故、事件に巻き込まれた人やそれらを目撃した人が発症することでも知られています。
ですが、このような深刻な事態に遭遇した人すべてがPTSDを発症するのだろうかという問題は心理学の世界でも疑問視されるようになってきました。被災した人のなかには、むしろ人生を肯定的に受け入れるという変化を生じる人もあらわれたのです。
たとえば、「あんな目にあったのに、自分はこうして平穏に生きていられる」という日々への感謝があります。危機的な状況を体験した人すべてがPTSDを発症するわけではなく、むしろ、ポジティブな変化に転じることがあると近年の研究ではわかってきています。
具体的にあげていくと次のような変化です。
・他者への思いやりが強まる。自己中心的な考え方から他者に優しくできるようになる。
・新しい人間関係の構築。トラウマ的な出来事を契機に、周囲の人間関係を見直しができる。信頼できる友人ができる。
・自分自身の変化。困難に打ち勝つ強さを身につけたり、自分らしさを大切にできるようになる。
・感情のコントロールが可能になり、怒りを爆発させることがなくなる。
・命の大切さに気づく。
細かく上げていくときりがありませんが、人として成長を遂げている姿が目に浮かびます。
このようなポジティブな心理的変化を『PTG(心的外傷後成長)』と呼びます。
苦しみやつらい出来事は確かに大変なストレスに感じられますが、同時に当事者の人生を豊かなものに変える可能性を秘めていると言えるでしょう。
この『PTG』の考え方を休職というつらい出来事に当てはめたとき、私たちは何を得ることができるでしょうか。
休職はトラウマ的なライフイベントに終始せず、休職者の人生をポジティブなものへと変化させる可能性があるということなのです。
ここで一つ強調しておきたいのは『PTG』は、全ての逆境に遭った人に経験されるものではないということです。『PTG』の研究はまだ始まったばかりで、詳細なプロセスなどについても研究の蓄積は足りません。
しかし、現実に『PTG』を経験している人々がいるからこそ、この“こころの回復力”は脚光を浴びています。
では、具体的に『PTG』をどのように休職にいかしていくかを考えていきたいと思います。
先にも述べた通り、休職は当事者にとっては、人生の危機にも相当するつらい出来事かもしれません。このような出来事を経験せざるをえなかったとき、私たちは苦悩し、もがき苦しみます。
先が見えない暗闇に放り込まれた気持にもなるでしょう。
ですが、この苦悩こそが不可欠なのです。自分自身を顧みるなかで、見えなかったものが見えてきます。新たな気づきを得ることができるのです。
気づきは実感をともなうこともあります。
たとえば、これまでの仕事に対する姿勢です。
自分さえ頑張れば、業務はうまく回ると無理をしすぎていなかったでしょうか。
会社のために役立ちたいと考え、頑張りすぎた結果、心身の不調を感じるようにならなかったでしょうか。
「つらかったなあ……」「しんどかったなあ……」という実感がわいてくると思います。
これが気づきにつながります。
「このままでは駄目だ」「もっとプライベートも楽しめるライフスタイルに変えたい」など、今までの自分を変えようという気持ちにつながるでしょう。
この気持ちが強いほど、変化へのモチベーションは高まります。
もう二度と同じ轍を踏みたくないと思えばこそ、病気の再発を防ぐ努力もしようと思います。
このように『PTG』のプロセスを活用することで、再休職予防のモチベーションを上げることも可能になります。
苦悩はつらいですが、決して無意味ではありません。休職者にとって、その出来事が人生においてどのような意味を持つか、改めて振り返るタイミングなのだと理解していただければと思います。
また、『PTG』における変化については、対人関係の価値観があります。苦悩していくなかで、自分ひとりではないこと、支えてくれる家族や仲間、社会的資源があることに気づきます。
この社会的資源に対する感謝の気持ちが、他者への思いやりにつながり、新たな可能性を拓いてくれることも研究でも示唆されています。
リワークにおいては、復職という同じ目標を持つ休職者たちの存在が、当事者にとって大きな意味を持つことがわかっています。
一人ではすべてを乗り越えられないことに気づく。
これだけでも、一人で仕事を抱え込みがちであった休職者には意味のある変化ではないでしょうか。困ったときには誰かに助けを求め、重荷を誰かと分かち合う。このような経験にともなう実感は、その後の対人関係を変えるでしょう。
自分も助けてもらったのだから、困っている人を自分も支えていこう。
意識の変化はこのように生じます。
休職というつらく、苦しいライフイベントも、このような視点を取り入れると、人生を変えられる契機にならないでしょうか。復職後のライフキャリアをより豊かにするためにも、『PTG』という考え方をぜひ取り入れていただきたいと思います。
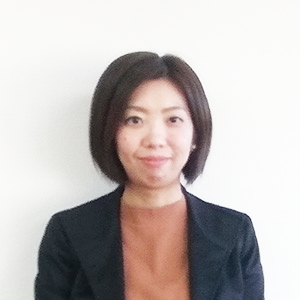
関連するコラム