うつ病からの職場復帰。復職後に安心して働くために事前準備が不可欠
うつ病で休職し、少しずつ回復してくると、家で療養していることに焦りを感じ始めます。業務から離れて、休んでいることへの罪悪感もあるでしょう。一日も早く現場に戻りたいと考えてしまうのは、自然な反応に違いありません。
ですが、そのタイミングでの職場復帰は本当に適切でしょうか? 復職して業務に耐えられるだけの状態まで回復しているのでしょう
今回は、うつ病の回復の仕方の特徴と職場復帰の目安について紹介
うつ病で休職し、少しずつ回復してくると、家で療養していることに焦りを感じ始めます。業務から離れて、休んでいることへの罪悪感もあるでしょう。一日も早く現場に戻りたいと考えてしまうのは、自然な反応に違いありません。
ですが、そのタイミングでの職場復帰は本当に適切でしょうか? 復職して業務に耐えられるだけの状態まで回復しているのでしょう
今回は、うつ病の回復の仕方の特徴と職場復帰の目安について紹介

病気の回復をイメージするとき、一般的には右肩上がりの直線が思い浮かぶかもしれません。
ところが、うつ病の回復の仕方を図にすると、独特な波線を描きます。症状が悪化している時期を谷間と考えると、心身の調子は波線を描きながら徐々に回復していきます。
最初に述べたような、直線状の回復ではないのが特徴です。きれいな右肩上がりでないという、この波線状がくせもので、うつ病の治療の難しさでもあります。
もちろん回復はしていくのですが、その途中に好調な時期と不調な時期が交互に訪れます。
「調子が良くて回復してきた」と喜んでいると、次に気分の落ち込みがやってきます。気が滅入り、やる気が出ないとふさぎ込んでしまう時期が来るでしょう。
どうして自分はダメなんだ、と責めたくなるところですが、ここがうつ病の治療のポイントです。
うつ病は周期性の病気なので、症状のアップダウンはつきものです。
しんどいときが来れば、意欲的になれる時期も来ます。物事を悲観的にしか見られないときは、このままよくならないのではないか、と不安に駆られるかもしれませんが、主治医とよく相談しながら、治療を続けることが大切です。
うつ気分が強くなるようなら、うつに効く薬を増やしてもらうことも可能ですし、不安が強いようなら、気持ちを落ち着かせる薬を出してもらう相談をするのもいいでしょう。
とにかく、一人で抱え込み、症状を悪化させることだけは避けねばなりません。何か気になることがあれば、すぐに相談できる環境を整えておくことが重要です。そのためにも、主治医とは、どんな細かな報告でも行っておくことをお勧めします。
また、家族のアドバイスも、視野が狭まっている状態のときには助けになります。
うつのときには重大な決断をしてはいけないとよく言われますが、ものの見方が普段と違い、判断力も低下しているためです。そのような状態のときは、まず結論を出すのを先延ばしにすることを勧めますが、どうしても、という場合は、家族や主治医と話し合って決めるほうがよいでしょう。
どんな結論を出しても後悔するのが、うつ病の不調な時期なのです。
無理をして決断するよりは、より回復し、好調の波が来ているときに考えをまとめるほうが得策です。
うつ病の症状はアップダウンを繰り返しながら、徐々に回復していくことを説明しました。
不調の谷の時期と、好調の山の時期を交互に繰り返し、少しずつ本調子に近づいていきます。階段のステップを上がるイメージで考えるとよいでしょう。
一段ずつ階段を上っていくと、気分も安定し、動けるだけの体力も戻ってきます。
症状が落ち着き、
ここで強調しておきたいことは、主治医から「復職可」の診断が下りても、休職前の状態と同じに戻ったわけではないということです。
主治医の「復職可」の判断は、あくまで「働ける状態まで回復した」という意味であり、復職前と同じ程度までよくなっている、という意味ではありません。このことを知らないままいざ復職すると、症状の再燃、再発のリスクが増しますので注意が必要です。
では、主治医の判断が間違っているのではないか、と考えてしまいますが、それは違います。
主治医は患者が休職する前、どのような働き方をしていたかを基準に判断しません。一般的に働ける程度を目安に、この回復状態なら働いても大丈夫、と許可を出します。
休職前の業務量、業務の質、残業時間や対人関係など、診察のなかで把握していたとしても、その状況に耐えられるかどうかでは判断しないのです。
ここにうつ病の復職の落とし穴があります。
職場がイメージする回復状態は、休職前のあなたです。ですが、医師が復職可と診断したあなたは、まだその状態まで戻っていません。あなたが実際に働き始めたとき、職場が期待する働き方ができないと落ち込むかもしれませんが、その場合、最初に職場が設定した復職後の業務のハードルが高すぎる可能性があります。
復職後、すぐに休職前と同じ状態で働けるとイメージしていると、思うように動けない自分に落ち込むことも出てきます。
うつ病は長く付き合っていく病気です。復職した時点で治療を中断するのも危険です。働き始めても治療も継続しながら、病気が良くなる日を待ちましょう。
うつ病は周期的にアップダウンを繰り返す病気だということを伝えてきました。復職可と医師が判断しても、アップダウンがなくなるわけではありません。
不調の波、谷の部分がやってきても、勤務に耐えられると判断されるとき、復職可の診断がおります。しかし、谷の部分が底上げされただけで、好不調の波は依然として残り続けます。
好調のときはよいですが、不調の谷に落ち込む時期も含めて、職場にあらかじめ復帰のための環境を整えてもらう必要があります。
可能なかぎり、休職期間中から人事担当者や上司など、復帰後の環境調整を依頼できる相手と連絡を取り合っておきましょう。担当者に病気についての理解を深めてもらい、スムーズに復職するためです。
配置転換を含め、時短勤務から始めるのか、慣らし勤務はあるのか、など職場によって復職者への対応は様々です。主治医や産業医の意見も伝えることで、無理のない働き方で復職することは可能です。
大事なのは、最初から、休職前と同じレベルのパフォーマンスを自分に求めないことです。
職場に復帰したての頃は、
以前の自分なら処理できた業務量をこなすことができない
周囲と比べると、自分の仕事は足りていない気がする
チームのなかで自分は足を引っ張っているのではないかと思う
これらは復職者が感じることが多い自責の気持ちです。
もともと、復帰したての時期というのは、本調子ではありません。
足を骨折した人が、
全力で走れば当然、骨折は悪化しますし、
うつ病もこれと同じです。
職場に復帰したての時期というのは、
そのときにできるベストを尽くせばよく、無理をすることは得策ではありません。
最初は短い時間から働き始め、負担の少ない業務を担当するように配慮を求めてください。
可能であるなら、対人関係もストレスのかからない配置に異動させてもらうのもよいでしょう。
このような環境調整は決して怠けでも甘えでもありません。
病気を治し、しっかりと働けるようになっていくために必要な、事前準備です。復職前に担当者と話をし、このような準備をしておくことをお勧めします。
自分がおくれを取っていると焦る気持ちをぐっとこらえ、納得のいく仕事ができるようになるためにも、無理をしない環境づくりをあらかじめ職場で整えてもらうことが大切です。
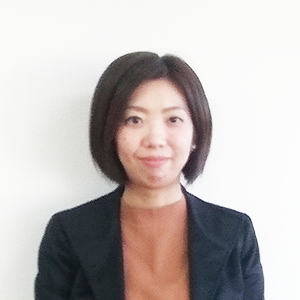
関連するコラム